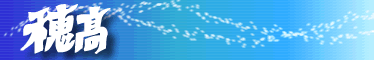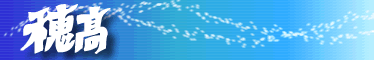| 低酸素と登山活動 |
以前、北アルプス蝶ヶ岳のテント指定地で幕営中、親子登山をしていた高校生が夜中に体調の不調を訴え、翌朝ヘリで救助されましたが、搬送先の病院で亡くなりました。死因は肺水腫でした。また、同じく蝶ヶ岳から常念岳の稜線上で夏山合宿をしていたR大学ワンダーフォーゲル部のリーダーが体調不良を訴え、ヘリで搬送され肺水腫と診断されました。高山病とされている肺水腫に至る例は3,000m付近の日本アルプスの環境下では例が少ないものの現実です。しかし、日本アルプスの標高を越える富士山では、急性高山病と思われる疾患でひと夏で4名が死亡された例も現実です。高山病にまで至らないにしろ、低酸素が起因となった体調不良を訴え夏山診療所等で診察をうけている登山者は多いのではないでしょうか。
登山者が活動中環境から受けるストレス(障害)の要因は1)低気圧・低酸素、2)低気温、3)雨、風、などがあげられます。この中で、2)低気温は、防寒具とで防御が、3)雨、風は、雨具で防御が、それぞれ可能ですが、1)低圧・低酸素の防御装備はありません。そこで低酸素が人に与えるメカニズムと予防について考えてみます。
人の体は自覚症状こそないかもしれませんが、標高2,500m付近まで急激に上がると約30%の人が、標高3,500mではほとんどの人に山酔い症状が表れるようです。主な症状は、頭痛・嘔吐で、他にめまい・倦怠感・食欲不振・睡眠障害などです。
では、実際に気圧高度計とパルスオキシメーター(光を当てることによって血中酸素飽和度を測る計器。通常の血液は光をスムースに透過させるので高い数値が表示されます。粘度の?高くなった血液は、光がスムースに透過しないので低い数値が出ます)を使って日本最高峰の富士山の気圧とからだの中の酸素飽和率の変化を見てみましょう。
気圧高度計を刈谷市の生活環境、標高0m(ほぼこれに近い)として、1気圧=1,013ヘクトパスカル(以下hPa)に設定して推移してみました。パルスオキシメーターのデーターも刈谷市を生活レベルとして、5合目・7合目・8合目・頂上とを比較しています。 |
 |
 |
| 気圧計を刈谷の生活環境で1,013hPaに設定して、このまま富士山に持って行き変化を見てみました。 |
被験者の1,013hPaでの血中酸素飽和度。左の数値97%が飽和度で、右の数値65が1分間心拍数です。 |
| 大気中の酸素量はどの環境でも21%含まれています。大気圧に対しての酸素比率を酸素分圧といいます。刈谷の酸素分圧は1,013hPax0.21=約213hPa |
| 10時に刈谷を出て、東名高速道路で富士インターを経て、国道139号線経由で河口湖へ、スバルラインで5合目へ。所要時間約4時間30分でした。 |
 |
 |
| スバルライン5合目、標高2,300mでの気圧計。779hPaを示しています。刈谷から234hPa下がりました。約25%の減圧です。ここでの酸素分圧は779hPax0.21=約164hPaで49hPa下がりました。 |
スバルライン5合目に着いた時のデーターですが、心拍数はほぼ同等で血中酸素飽和度は93%と刈谷から4%低くなっています。この段階では体調のさほどの変化を感じません。 |
| 5合目で1時間ほど滞在して、15時30分に行動を開始し、本日の宿泊地7合目まで、2時間かけて移動しました。 |
 |
 |
| 標高2,700mまで上がってくると大気圧も744hPa刈谷から269hPa下がりました。ここでの酸素分圧は744hPax0.21=約156hPaで57hPa下がりました。 |
血中酸素飽和度も88%と刈谷から約10%減少しましたし、心拍数も上がっています。ちなみにこの標高で90%をわった飽和度を示したらちょっと注意が必要ですね。 |
 |
7合目の小屋に泊まって朝起きて朝食前の血中飽和度です。昨日ここに到着したばかりのデーターよりはるかにいいデーターが出ています(1,013hPaの酸素分圧の刈谷と同じ飽和度です、ちょっと信じられない部分もありますが)。5合目に到着してから12時間以上ほぼ同等な酸素分圧の環境で生活したことによる順応の結果でしょうか? |
| 7合目の小屋を朝5時30分に出発して、標高3,450mの今日の宿泊地、8合5尺の小屋に向かいます。1時間で稼ぐ標高は約200mと歩行スピードはほんとうにゆっくりです。特にこの間は、登山道の傾斜もきつく、岩がゴロゴロしているので、頂上までの登山道では、もっとも歩きにくい環境といっていいでしょう。そして最も筋肉を使うので、ほとんどの登山者はこの間に受けたダメージが大きくて敗退となるようです。約3時間かけて途中の3,200mの8合目に到着しました。 |
 |
 |
| 標高3,200mの8合目までやってきました。気圧は716hPa。刈谷から297hPaも減圧してきました。酸素分圧は716hPax0.21=約150hPaで63hPa下がりました。 |
昨日7合目の小屋にたどり着いたときは88%だったのに対し、酸素分圧が減圧したにもかかわらず、血中酸素飽和度は92%と上がっています。順応した朝の体の調子をそのまま維持しているようです。 |
|
3,450mの8合5尺の小屋までの予定でしたが、天気も体調もよさそうなので、今日中に頂上に行くことにしました。7合目の小屋を出発してから6時間、3,776mの山頂にたどり着きました。
|
 |
 |
| 被験者、兼カメラマンの技術が悪いので、見にくいデーターですが、3,776m頂上のデーターです。気圧は661hPa。刈谷から352hPaも減圧しました。酸素分圧は661hPax0.21=138hPaで149hPa下がりました。約35%も少なくなってしまいました。 |
同様に見にくいかもしれませんが、飽和度はついに80%も割り、76%、心拍も100を数えました。刈谷より20%も減少しています。さすがにこのデーターはイエローカードですが、体感は息が上がる程度で、それ以上のストレスはまったくないようです。 |
頂上で、頭痛・吐き気などの症状を訴えている登山者の血中酸素飽和度は70%をも割っている人もいるでしょう。医療レベルから見てもレッドカードです。仮に、被験者と同じくらいのデーターでも、このように時間をかけてゆっくり達しなければ、苦しさは計り知れないものになります。
頂上から一気に5合目に下ろうと思いましたが、予定の8合5尺の小屋に泊まることにしました。優雅でゆとりのある登山プランです。この行程なら、初心者でも登頂確率100%に近いでしょう。 |
 |
 |
| 3,450mの小屋ですから、頂上からの高差は300m。気圧の差も、頂上とさほど変わりません。 |
この標高での飽和度としては、レッドカードです。頂上の時より悪い70%の飽和度を割ってしまいました。酸素分圧は頂上と差はないといえども、多少は上がっていますから、常識的には頂上よりいい数値を示すはずです。やや頭痛があったようです。 |
昨日の2,700mの7合目の朝は、平地と同様レベルの順応を示しましたが、生活レベルの65%しかない酸素分圧の3,450m環境まで上がってくると、順応も同等ではないようです。起床時の飽和度が最も下がっているデーターです。計測は登山行為中ではなく登山生活時とこのように起床時に計測することが望ましい)。被験者の体調はデーターほど悪くありません。この後は少しずつ順応に進んでいくと思われます。今回は富士山中で2泊してみました。起きて活動している時は自立神経が活発に働くので呼吸も脳が指示するため、体の器官が酸素飽和度を極端に下げる可能性は低いのですが、睡眠に入ると自律神経の活動が低下するとともに、呼吸も低下し各器官の酸素飽和度も下がってしまいます。事実、被験者は昨日の2,700mの7合目小屋での睡眠体感より、はるかに寝苦しい体感をしました。睡眠中の呼吸数低下により体内酸素飽和度がさらに下がったことで、そのつど脳が「起きて呼吸しろ!」と信号を送るから寝苦しく感じるのでしょう。仮にこの高さに2日間も滞在すれば順応が進み、日常と同じような睡眠が可能になります。
このように、環境が低酸素分圧に変化していくと、人間の体の中の血液に大きな変化が生じます。頭痛・吐き気・倦怠感・などの代表的な症状の起因はこの血液変化が犯人かもしれません。高山病というより、むしろ生体反応による症状といった方が正しいのでしょうね。
人間は急性にとても弱い生き物です。一気に急いで行わず、徐々に慣らしていく、運動生理学でも漸増性の法則があるように、余裕のあるプラン作りから初めて「慣れながら」進んでいきましょう。
さて、赤血球の量が上がり、血流が悪くなった血液はどうにもなりませんが、血流の助けになるのが水分です。ということで、登山をする前、登山中、どのように、どれくらいの水分を摂っていったらいいのかをアドバイスしてみます。
そして、低酸素ばかりではない富士山の環境の変化を人間がどのように感じるのかも、アドバイスしてみます。 |
| 登山活動と水分補給 |
登山活動は、運動時間が長いことや、環境が低酸素となるため、必然的に多くの水分が必要となります。登山活動では、水分補給を怠ると「脱水」を起こします。脱水のさまざまの障害は、
1)熱疲労といって、血液中の水分量までも減って血圧が下がり、各期間への血液循環が悪くなり酸素運搬量が減ることにより、倦怠感・息切れ・頭痛・めまい・嘔吐などの症状がでます。
2)熱痙攣といって、発汗によって水分、塩分が大量に失われ、筋肉中の電解質のバランスが崩れ、登山中は主に、ふくらはぎや、太ももの筋肉に痙攣が起こります。
3)むくみも脱水障害のひとつで、脱水が進むことによって生体がそれ以上の水分を失うまいとして尿を制限させます。本来は排出しなければならない水分が蓄積された症状です。山中で宿泊した翌日が最も多いのですが、下山して1〜2日続くこともあります。
4)血栓といって血液中の水分不足により、血液の粘性が高まり、血液が固まりやすくなります。中高年者の脳梗塞、心筋梗塞などの起因のひとつです。
5)みなさんよくご存知の熱中症で、熱射・日射で体温が上昇し続け、発汗は停止し、運動の失調や意識の混濁がおこり死亡例の多い障害です。私の友人は、熱中症の熱射がもとで、肝臓・腎臓障害の合併症を起し、人口透析をしながら1ヶ月入院していました。
登山活動中には平均して、体重1kgあたり、1時間の運動で5mlの水分が失われるようです。体重60kgの人が、1時間行動すると300mlの水分を失うことになります。さらに、8時間も行動すれば何と、2,400ml(2.4リットル)も失います。このことから登山中の水分摂取は、失う水分を補給することを目標にします。不便で不自由な山岳地帯で、計算通りの水分が摂取できるか?ということにもなりましょうが、水分補給ができる環境を把握した上で、最大限の摂取を考えるべきでしょう。
脱水の障害は、脱水量が体重の2%を越えると起きやすいといわれています。体重60kgの人だと1.2kg=1,200ml(1.2リットル)の水分を失うと脱水が始まります。登山活動の平均脱水量から換算すると、4時間水分摂取せずに行動することになります。8時間登山活動していて、1.2リットル以下の水分摂取しかしていないのも同等行為です。
脱水は、自分自身の持久力以上のオーバーワーク行為が加わると急促進されることも忘れてはなりません。日焼けも同等に促進します。急性的に強い紫外線を受けた顔、肌を出した腕、首筋は、真っ赤に日焼け、皮膚温度がどんどん上昇し、気化熱によっても水分を失います。急性的熱中症障害の予防のためにも、襟付き・長袖シャツの着用と、顔などの薬用日焼け止めには気をつかうことが大切です。
さて、脱水は大量に出る汗だけと思われがちですが、低気温であまり汗をかかない冬山や、低圧・低酸素の高所でも進行しています。恒温動物の人間は、体温が必要以上に上昇し始めると、体温を一定に保とうとして発汗するため、水分を失います。それに対し低温化の冬山では、体温を下げまいと代謝(産熱)するため水分が使われます。また低酸素高所環境でも、生体反応として基礎代謝量が上がるため、同様に水分が使われます。また、登山行為の呼吸によっても、体重1kgあたり、1時間に平均1ml失います。オーバーワークを続けたときの呼気は脱水の危険信号行為です。
さて、水分の摂取方法ですが、時間脱水水分を休息時に摂ることです。60kgの体重の人の1時間に失う水分は300mlですから、基本的には時間脱水量をコンスタントに摂取します。飲み物は最近たくさん販売されているミネラルウォーター類がいいと思います。これらの水分の中には、ナトリウム・カルシウム・カリウム・マグネシウムなどの汗で失う、ミネラルが含まれているため効果的です。特に発汗量が多めだと予測できる環境ではスポーツドリンク類の方が汗で失うナトリウムの含有量が多いので効果的でしょう。
水分補給の理想論を述べてみましたが、登山活動実際では、不足気味が現実です。登山活動が終了してからも、就寝時まで継続的に摂取しましょう。この場合は嗜好品が飲量欲が出ていいと思います。「飲むから出る」、「出るから飲む」。というような、心地よく定期的に繰り返される排尿行為が、正常な循環機能の働きの指標でしょう。
ウォーターローディング(水分貯蓄)
登山活動以前に、体内に十分の水分を貯蓄しておくことも、長時間運動する登山活動に役立つ行為です。具体的には日常生活から脱水の体を作り上げないように、最低限脱水が始まる体重の2%の量の水分を毎日定期的に摂取することを日課にします。60kgの体重なら、最低1.2ml(1.2リットル)の水分を起きて生活している時間内に摂取すればいいことになります。登山活動の水分摂取方法を習慣的に身につけるなら、1時間ごとに150ml摂取を継続するといいでしょう。熱中症が原因で、肝臓・腎臓障害の合併症を起し、人口透析をしながら1ヶ月入院していた友人の原因を探ってみると、登山行動中の水分摂取は、理想に近い量を摂っています。夏場を迎えて、入山前の日常生活で、お酒好きが災いのもととなり、冷えたビールを中心に水分を潤っていたのでしょう。冷えたビールは、一気に体を冷やす効果もある為、排尿の量も、飲んだ量の2倍ほどともいわれています。夏のゴルフ場で脳梗塞疾患の多いのも、犯人は案外ビールかもしれませんね。飲んだ分以上の水分も時間をかけて補充することを心がけましょう。 |
| 高度と気温・風 |
山の気温は平地に比べて低いことはおおよその想像の通りです。平地付近では太陽からの日差しを受けて空気が暖められ早い時間で昇温しますが、標高が高くなるにつれてこの影響が少なく遅くなります。標高が高くなるにつれて気温が低くなっていく現象を「気温の減率」といいます。この現象はその時々の天気や湿度などによって異なりますが、平均的に標高1,000m上がるにつれ約6℃くらいの割合で低くなっていきます。この減率からみて、平地の真夏の日中の気温が30℃とすると、夏山人気No.1?の富士山、3,776mでは21℃下がり約9℃以下と予測されます。しかし、経験上の実感は、穏やかな晴天時なら強い日差しを受けて汗ばむような暑さを感じています。これは強い紫外線が山肌の土、岩を熱し、山肌に接している空気層がその影響を受けて気温が上昇しているためですが、雲が出て紫外線も少なくなり、天候の悪化がはじまると風を伴い、山肌周辺の暖かい空気を吹き流し、周囲からは新たな冷たい空気が運び込まれて気温は下がります。この時の気温は「気温の減率」に従った気温、あるいはそれ以下になります。1日の気温は最高気温と最低気温があり、平地の最高気温30℃、最低気温20℃なら、富士山頂の最高気温は9℃、最低気温は氷点下1℃となります。したがってここでの登山者のみなさんは、氷点下1℃の気温に対応できる防寒着が必要ということです。富士山ばかりではなくその地域でも「気温の減率」から最低気温も予測して適切な防寒着の用意をしましょう。
風は地球上の大気の流れのことで、温度の域と気圧の域から成り立っています。そしてその両域の較差によって風の向きや強さが異なっています。北半球の日本では北極が低温で気圧が低く、赤道付近では気温が高く気圧も高いため偏西風が吹くことになり、平地より、標高の高い山岳地帯のほうが、夏季より冬季のように温度差が大きくなるほど風は強いといえます。この風は登山者の「体感温度」に大きな影響を与えます。「体感温度」とは、実際にカラダに感じる温度のことで、気温そのもののほかに、吹きつけてきている風の強さ(風速)でも変わります。一般的には風速1m/秒で体感温度は1℃低温になるといわれ、上記の例の平地の日中の気温が30℃のときの富士山の頂上は9℃、そこに風速10m/秒の風が吹きつけると、体感温度は氷点下1℃になります。氷点下1℃の最低気温を記録する時間帯だと体感温度は何と氷点下11℃まで下がります。経験上の実感は穏やかな晴天時なら汗ばむ暑さが、風によって快い体感にしてくれることもありますが、天候が崩れはじめ紫外線が少なくなると、氷点下1℃に近い体感になり、さらに身体が、雨・発汗によって濡れているとその気温の体感どころではなく、体温まで奪われることになります。恒温動物の人間の体温は、環境の温度変化に対して一定の体温を保とうとする機能をもっていますが、それを上回る環境の防御を怠ると「低体温症」となり、致命的な結果が凍死です。夏の高山では凍死に至る例はほとんどありませんが、行動不能状態で救助される例は少なくないようです。防水・透湿性の高い雨具、防寒具が装備として重要視される所以だと思います。
By す〜さん
参考文献 「登山の運動生理学百科」山本正嘉著・東京新聞出版局
「登山医学入門」増山茂著・山と渓谷社
「山岳気象入門」村山真司・岩谷忠幸著・山と渓谷社 |
|